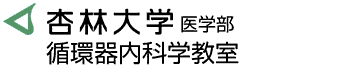心不全
心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です。あらゆる心臓疾患が最終的には心不全に繋がります。少しでも心臓の力を回復させるためには、薬などの治療とともに、患者さんご自身の日常生活の管理がとても重要です。
心筋症とは、心臓が拡張や肥大した結果として、心機能に障害が出る状態です。原因は様々ですが、特発性心筋症(原因が心臓にある)と二次性心筋症(全身疾患の中で心臓にも病変が起こる)に分かれます。特発性心筋症には拡張型心筋症や肥大型心筋症があり、二次性心筋症には心サルコイドーシス、心アミロイドーシス、ファブリー病などがあります。近年、心不全・心筋症に対する治療薬が著しく発展しています。

心不全チームの理念
- 一人一人の患者さんと真摯に向き合い、患者さん中心の心不全・心筋症医療を提供します
- 深い知性と豊かな人間性を有し、全人的医療を提供する医療人を育成します
- より良い心不全・心筋症診療・ケアを追求するために、チームで挑戦しながら成長します
心不全チームの診療
1. チームで最善の心不全・心筋症診療を提供します
心不全・心筋症外来
対象となる主な疾患は、心不全、拡張型心筋症、肥大型心筋症、二次性心筋症 (心アミロイドーシス、心サルコイドーシス、ファブリー病など)です。
また、虚血性心疾患・弁膜症・不整脈が主な原因の場合には、それぞれの循環器サブスペシャリティチームと密に連携し、最適な治療を進めます。
大学病院としての強みは「総合力」にあります。併存疾患を有する複雑な症例に対しても、腎臓内科・呼吸器内科・脳神経内科など他診療科と横断的に連携しながら、個々の患者さんに最適な医療を提供します。また、遺伝学的検査や先進的な画像診断、臨床研究を通じて、最新の医学的知見を診療に反映させています。
心不全・心筋症診療は、医師だけでなく、看護師・理学療法士・管理栄養士・薬剤師などからなる多職種チームの”集合知”によって支えられています。私たちは、深い知識と多様な価値観を持った仲間との議論・提案・検証を重ね、一人ひとりの患者さんにとって最善の心不全診療を追求いたします。
心アミロイドーシス診療
当院は2020年よりATTR心アミロイドーシスに対する疾患修飾薬導入施設として地域医療に貢献してきました。引き続き地域の病院からのご紹介をお受けし、血液内科、脳神経内科、放射線科との連携を行いながら、最善の診断体制で治療を提供してまいります。
2. 重症心不全診療に挑みます
植込型補助人工心臓実施施設
あらゆる治療に抵抗性を示す重症心不全に対して、高い“専門知”をもって最後の砦として診療しています。昨今、植込型補助人工心臓(VAD; ventricular assistant device)の発展があり、今後ますます知識や経験が必要とされる分野です。杏林VADチーム(循環器内科医、心臓血管外科医、看護師、臨床工学技士ら)は、植込型補助人工心臓実施施設として心臓移植施設と密な連携を維持しながら、最良の重症心不全治療を提供しています。
3. 心不全の発症・重症化予防を推進します
心臓リハビリテーション
心臓リハビリテーションは、心臓病の患者さんが体力を回復し、自信を取り戻して、快適な家庭生活や社会生活に復帰することを目的としたプログラムです。さらに、生涯にわたり再発や再入院を防ぐことも目指しています。このプログラムには、医師、理学療法士、看護師、薬剤師、管理栄養士など、多くの専門職が関わります。心肺運動負荷試験の結果をもとに、患者さん一人ひとりの状態に合わせた最適な運動処方を行い、入院中から退院後、さらには維持期まで継続してサポートします。また、仕事と治療の両立支援にも対応しております。

睡眠時無呼吸診療
いままで医師は診断と治療が一番重要な仕事でしたが、これからは予防や、健康教育、そして再発防止や重症化予防が極めて重要です。私たちが力を入れてきた睡眠時無呼吸診療の”経験知”を通して、循環器疾患予防を進めます。予防行動の輪を広げるために、糖尿病・内分泌・代謝内科、耳鼻咽喉科、精神神経科などや実地医家の先生方との密な連携を大切にしています。大学病院だからこそ可能な、診療・教育・研究を融合した予防医療の推進を目指しています。
4. “科学的根拠に基づく医療”と”患者さんの価値観に基づく治療”を大切にします
私たちは、科学的根拠に基づく医療(EBM; evidenced-based medicine)により、薬物治療の微調整・最適化を進め、各種の非薬物治療を適正に提供します。一方で、心不全診療には、EBMが明確に示されていない曖昧な部分も決して少なくありません。意思決定支援や心不全緩和ケアが重要な場面も多くなっています。患者さんと信頼関係を築くコミュニケーションを大切にし、患者さんの価値観に基づく治療目標を意識しながら、病気のことを知っていただき、最善の治療を一緒に考えます。